
養育費を請求したい・請求された

養育費を請求したい・請求された
養育費の請求
夫婦間に子供がいる場合、離婚前に子供の養育に必要な養育費の金額や支払期間について取り決めを行っておくことが推奨されます。
本ページでは、養育費の性質、算定方法、請求手続、義務者が支払わない場合の強制執行、事後的な養育費の増減額について解説いたします。

1 養育費とは何か?

1.1 親権の内容
民法は、「父母が協議上の離婚をするときは、(中略)子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」(民法第766条)と規定し、子供の監護費用(養育費)の支払義務を定めています。
上記義務は、「親の子に対する扶養義務の現れである養育費は、扶養義務者の生活に余裕があるときに扶助するというもの(いわゆる生活扶助義務)ではなく、扶養義務者の生活費を削ってでも要扶養者の生活を保持させるためのいわゆる生活保持義務である」(東京高判平成24年8月29日(平成24年(ネ)第3197号))とされているところ、親は未成熟の子供に対し自身と同程度の生活を送ることができる金額の生活費を支払う義務を負うことになります。
なお、婚姻中の養育費は婚姻費用の中に含まれることから、婚姻中の場合には婚姻費用を請求すれば足ります。
1.2 始期と終期
実務上、当事者間で合意できない場合の養育費の始期は請求時とするのが一般的です。
具体的には、権利者が義務者に対し内容証明郵便により婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した場合には意思表明時、内容証明郵便の送付等を行わず養育費請求調停を申し立てた場合には調停申立時が「請求時」と判断される傾向にあります。
なお、出生時まで遡って養育費の支払を命じた裁判例(大阪高決平成16年5月19日家月57巻8号86頁、名古屋高決令和2年2月28日(令和元年(ラ)第216号))もあります。
しかし、このように養育費の始期を出生時まで遡ることが認められるのは、養育費請求の前に認知請求を行う必要があったなど特段の事情が存在する事案のうちごく一部に限られます。
以下の司法研究報告書によれば、養育費の終期(当事者間で合意できない場合)は、両親の学歴、収入、進学に対する両親の意向などの個別的な事情に照らし、子供が自立すべき時期と判断される時点と考えられます。
具体的には両親の学歴や収入、進学に対する両親の意向等から子供が大学に進学する可能性が高いといえる場合の養育費の終期は大学等の卒業見込月(満22歳に達した後の最初の3月)まで、上記可能性が高いとはいえない場合の養育費の終期は子供が満20歳に達する日の属する月までとされることになると考えられます。
司法研究報告書第70輯第2号「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」60頁
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに関連して、「改正法の成立または施行後の養育費の支払義務の終期は、それぞれの事案における、諸般の事情、例えば、子の年齢、進路に対する意向及び能力、予測される子の監護の状況、両親が子に受けさせたい教育の内容、両親の経済状況、両親の学歴等の個別事情等に基づく、将来のどの時点を当該子が自立すべき時期とするかの認定、判断によって決すべきこととなる。」
「例えば、子供が大学に進学することを希望しており、かつ、その能力もあると認められるなど、子の大学進学の可能性が高いと認められる場合であって、両親の学歴、経済状況及び子に対する従前の対応等により、非監護親に大学卒業までの生活費を負担すべき事情があると認定、判断されたときは、子が一般的に大学を卒業すると推認できる満22歳となった以降の最初の3月までを、養育費の支払義務の終期と判断すべきこととなる。」
「今後社会情勢等が変化しない限り、子が幼い事案など、子が経済的自立を図るべき時期を異なる時点と特定して認定、判断すべき事情が認められない事案においては、未成熟子である期間について、改正法の成立又は施行前と異なる認定、判断をする必要はなく、従前のとおり、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までとされることになると考える。」
なお、成人した子供が大学等に進学していないが持病により稼働能力が認められないという場合、子が未成熟子にあたる(子供が自立すべき時期が未だ到来していない)として非監護親の子に対する生活保持義務を認める裁判例(東京高決昭和46年3月15日家月23巻10号44頁)と非監護親の子に対する義務はあくまで親族間の扶養義務(生活扶助義務)として検討されるべきとする裁判例(大阪家審平成26年7月18日判時2268号101頁)があります。
1.3 遅延損害金の始期
「養育費に関する審判は,非訟事件として養育費分担義務を具体的に形成するものである」(名古屋高決令和2年2月28日(令和元年(ラ)第216号)とされています。
また、金額が決定された後の養育費は定期金債権であり毎月弁済期が到来します。
そこで、養育費の遅延損害金は具体的な分担額が形成決定された後、具体的には協議または審判で定めた支払期限の翌日から発生します(民法第412条第1項)。
1.4 支払方法
「養育費は,その定期金としての本質上,毎月ごとに具体的な養育費支払請求権が発生するものである」(東京家審平成18年6月29日家月59巻1号103頁)とされているところ、定期的に支払いを行うというのが原則です。
もっとも、配偶者に養育費を一括で支払うだけの資産がある場合や配偶者による養育費の定期的な支払を期待できない場合には養育費を一括で支払うとの内容で合意することもないわけではありません。
なお、その場合、事後的に養育費の増減額請求を行うハードルが高くなること、権利者が一括で受領した養育費を費消した後に子供から扶養料の請求があった場合には扶養料の支払義務が生じる可能性があること、贈与税の課税対象となるリスクがあること、養育費の義務者に相続が発生した時点以降の養育費支払債務は本来的には相続対象ではないものの一括払の合意をすることで将来分の養育費支払い債務が相続債務となること(相続発生時点で未払の場合)には注意が必要です。
1.5 扶養料請求との関係
民法上、子供から親に対する扶養料請求(民法第877条第1項)が認められています。
上記の扶養料請求権は子供自身の権利である一方、養育費請求権は子供の監護親(通常は親権者)が他方の親に対し子供の監護費用を求める権利であるという違いがあります。
そこで、通常、子供が未成年の間は監護親が他方の親に対し養育費の請求を行い、子供が成人した後には子供自身が扶養料の請求を行うことになりますが、成人した子供が未成熟子にあたるのであれば監護親が養育費を請求することも可能と考えられます(「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」59頁、東京高決平成29年11月9日判時2364号40頁参照。もっとも、親権者を決定しない関係で監護親性が争いになる可能性はあります。)。
なお、扶養料請求権と養育費請求権はいずれも親の子に対する生活保持義務を根拠とするところ、監護親が養育費を受領している中で子供が扶養料を請求した場合、扶養料から養育費が控除されるというのが一般的です(大阪高決平成29年12月15日判時2373号38頁、大阪高決平成30年3月15日判タ1457号91頁等参照)。
2 養育費の算定方法

2.1 改定標準算定方式の利用
養育費について父母が協議により定めることができる場合には、原則として父母間で取り決めた金額の養育費を支払うということで問題はありません(民法第766条第1項)。
しかし、父母間で養育費の合意ができない場合や合意の前提として養育費の目安を把握しておきたいという場合には、一般的な養育費の算定方法を抑えておく必要があります。
現在、養育費の算定方法としては、司法研究報告書第70輯第2号「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」が提案する改定標準算定方式が広く用いられています。
一般の方が養育費の目安を知りたいという場合には、上記改定標準算定方式による算定表を参照するのが簡便です。
※改定標準算定表については、こちらの裁判所Webサイトからご覧ください。
2.2 収入
改定標準算定方式は、基本的には父母双方の収入や未成熟の子供の年齢、数を基に養育費を算出します。
ここで、養育費算定の基礎となる父母の収入ですが、給与所得者の場合には源泉徴収票の「支払金額」や所得証明書の「収入金額」に記載されている税込みの収入額を指します。
一方、自営業者(事業所得者)の場合には確定証明書に記載の「所得金額」、「社会保険料控除」、「専従者給与(控除)額の合計額」「青色申告特別控除額」を基に以下の計算式で計算することが可能です。
自営業者の総収入
=「所得金額」-「社会保険料控除」+「青色申告特別控除額」+「専従者給与(控除)額の合計額」(現実に支払いがなされていない場合)
2.3 修正要素
特別の事情が存在する場合には、改定標準算定方式で算出した養育費を修正することがあります。
具体的には、以下のような費用負担が生じている場合には養育費加算の主張を行うかどうかを検討する必要があります。
加算要素
・子供が私立高校や大学に通っている場合:学費
・子供が保育園に通っている場合:保育料
・高額な医療費等が生じている場合:医療費等
3 請求手続
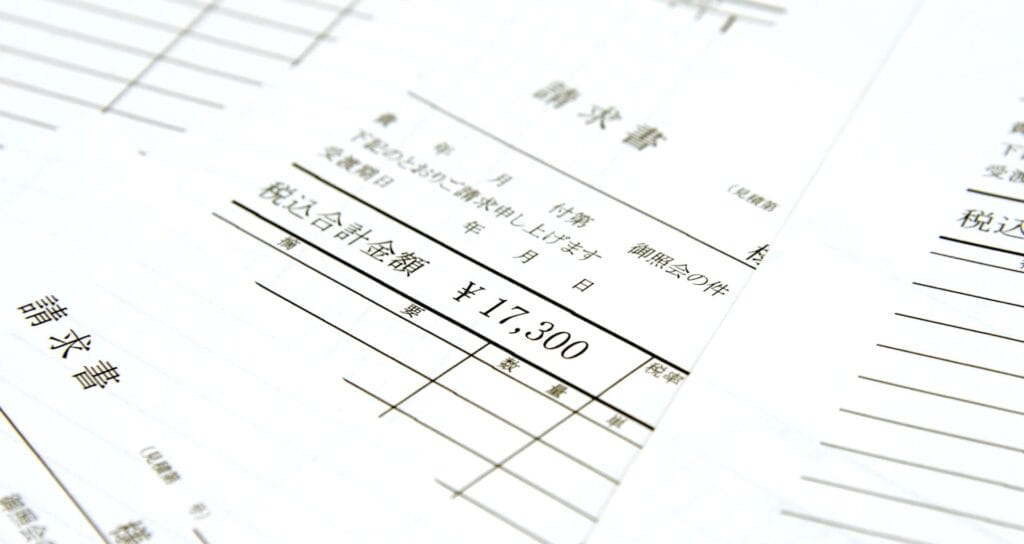
3.1 当事者の合意
養育費については父母が協議で定めることとされています(民法第766条第1項)。
そのため、まずは父母間で金額や支払期間について話し合った上で養育費について合意することが考えられます。
なお、父母間で養育費の合意をする場合、合意の確定性が問題になり得る点には注意が必要です。この点については、婚姻費用の合意に関するQ&A「夫が支払うと約束した金額の婚姻費用を支払ってもらえる?」が参考になりますのでご参照ください。
3.2 離婚調停・離婚裁判
協議離婚が成立しない場合には、調停や裁判により離婚を成立させることになりますが、その場合でも離婚と同時に養育費を決定しておくのが一般的です。
具体的には、離婚調停の場合には離婚調停に養育費に関する付随申立てを、離婚裁判の場合には養育費に関する附帯処分の申立て(人事訴訟法第32条第1項)を行っておくことで離婚に合わせて養育費を決定することが可能です。
3.3 養育費請求調停・審判
上記1.2のとおり、養育費の始期は請求時であることから離婚する際に養育費を取り決めておかない場合には養育費を請求できない期間が発生するおそれがあります。
そのため、養育費は離婚時に協議(上記3.1)や離婚調停、離婚裁判(上記3.2)の中で決めておくのがベストではあります。
もっとも、父母が離婚時に養育費を取り決めておらず、かつ、話合いで養育費の合意ができないという状況に至ることもあります。
その場合、養育費請求調停または同審判の申立てを行うことになります(なお、通常、審判申立てを行ったとしても調停に付される(家事事件手続法第274条第1項)ことになるため、調停の申立てを行うことがほとんどです。)。
調停はあくまで話合いの手続であるため当事者が合意できない場合には調停が不成立となりますが、その場合には調停申立ての時に審判申立てがあったものとみなされ、自動的に審判手続に移行することになります(家事事件手続法第272条第4項、別表2)。
審判手続では、最終的に家庭裁判所が審判により養育費についての判断を示します。
審判に対する不服申立てを行う場合
もしも審判に対して不服がある場合には高等裁判所へ即時抗告を行うことが可能(家事事件手続法第85条第1項、同第156条第3号)ですが、即時抗告は審判の告知を受けてから2週間以内に行う必要があります(同第86条第1項)。
また、即時抗告に対しては高等裁判所が決定を出しますが、当該決定に不服があるという場合には特別抗告(同第94条)、許可抗告(同第97条)という手段が用意されています。 特別抗告や許可抗告は即時抗告よりも期限が短く、裁判の告知を受けてから5日の普遍期間内にこれを行う必要があるため注意が必要です(同第96条第2項、同第98条第2項、民事訴訟法第336条第2項)。
養育費請求調停・審判の管轄
養育費請求調停の管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法第245条第1項)。これに対し、同審判の管轄裁判所は子の住所地を管轄する家庭裁判所になります(家事事件手続法第150条第4号)。
通常は相手方の住所地管轄の裁判所に調停申立てを行うのが一般的ですが、個別の事情に応じて別の裁判所に調停申立てを行うとともに自庁処理(家事事件手続法第9条第1項ただし書)の上申を行うこともあります。
4 執行手続

4.1 未払状態になったときは将来分の養育費を差し押さえることが可能
通常の債権の場合、履行期が到来後に限り強制執行を行うことができます(民事執行法第30項第1項)。
一方、養育費や婚姻費用など扶養義務等に係る定期金債権の場合には、その一部に不履行があった場合には確定期限が到来していないものについても債権執行を開始することが可能です(同法第151条の2)。
その結果、養育費や婚姻費用の一部に未払がある場合には、いったん差押えを行えば毎月の支払期限が到来する度に配偶者の預貯金や給与を差し押さえる必要がありません(配偶者が会社を退職した場合や預貯金残高がなくなった場合には別途対応が必要です。)。
4.2 差押え可能な範囲が広い
通常の債権の場合、給与に係る債権については手取り額の4分の1(手取り額が44万円以上の場合には33万円を超える部分)のみを差し押さえることが可能です(民事執行法第152条第1項第2号、同法施行令第2条第2項)。
一方、養育費や婚姻費用などの場合には、配偶者の手取り給与のうち2分の1(手取り額が66万円以上の場合には33万円を超える部分)を差し押さえることが可能です(民事執行法第152条第3項)。
5 事情変更による養育費の増減額
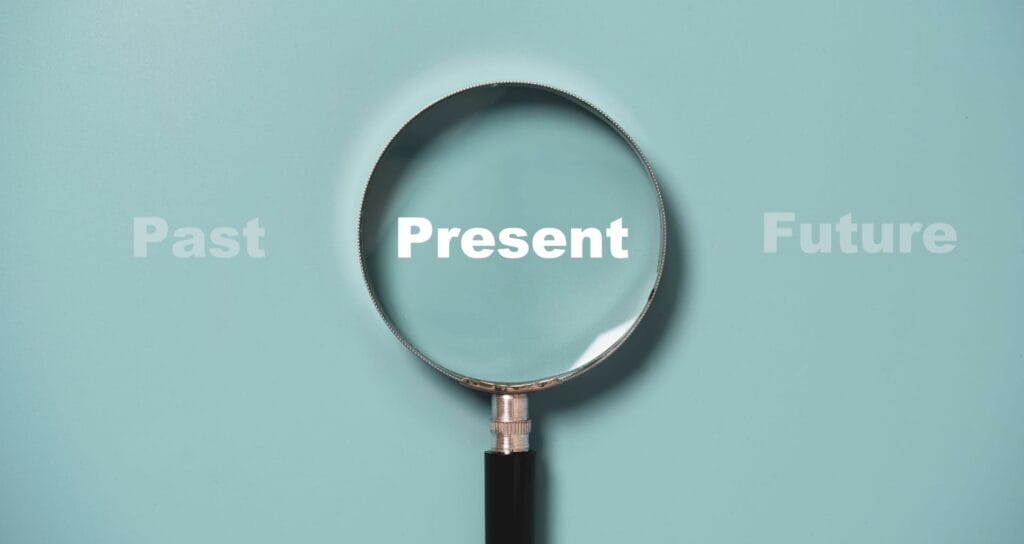
「養育費は、将来にわたるもので、当事者に身分関係、経済状態等の変化が生じることはやむを得ないことであり、それらが生じて養育費算定の基礎事情が変更し、それに照らして義務者が負担する養育費が不相当とみられる事態になったときは養育費の増減額を求めることができる性質のものである。」(東京高決令和5年1月31日令和4年(ラ)第1676号)とされているところ、養育費を取り決めた後に事情変更が生じた場合には養育費の増減額請求を行うことが認められています。
主な増減額事由は以下のとおりです。
5.1. 増額事由
・権利者の収入減少
・義務者の収入増加
・子供が満15歳に達したこと(東京高決令和3年3月5日(令和3年(ラ)第145号)
5.2 減額・免除事由
・権利者の収入上昇
・義務者の収入減少(養育費を免れるためなど不当な目的がない場合には転職を理由とする減収を含む(東京高決令和5年1月31日(令和4年(ラ)第1676号))
・義務者の扶養家族の増加
・義務者の再婚相手が無収入であること
・子供と第三者との養子縁組
・権利者が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組したのと準ずる状態にあること(宇都宮家審令和4年5月13日(令和4年(家)第3015号))
・権利者から義務者へ親権者変更が行われたこと
※本記事では養育費を請求したい場合及び養育費を請求された場合に押さえておくべきポイントをご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、養育費請求などについて検討されている方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。



