
離婚したいが進め方がわからない

離婚したいが進め方がわからない
離婚の進め方
離婚問題に直面した際に、まず何をしたらよいか分からないという状況に陥ることは少なくありません。
離婚する場合には、経済的な問題や子供の問題、離婚に至る原因や離婚後の生活など検討しておくべきことが多くありますが、これらの問題を事前に検討しておくかどうかで解決内容が大きく変わる場合があります。

1 離婚の進め方

現在、日本では結婚した3組に1組が離婚すると言われているため、離婚自体はさほど珍しくはないようにも感じられます。
しかし、多くの方にとって離婚は初めて経験するか、経験したことがあってもその回数が多くはないため、離婚を検討し始めた場合に何をすべきかが分からないという状況に陥りがちです。
また、結婚する場合とは異なり、離婚する場合には子供のことや財産のことなど決めるべきことが少なくないことも上記状況に拍車をかけています。
このような状況の中、「何をすべきか分からなかったため、とりあえず離婚届を提出して離婚を成立させた。」という方も少なくありませんが、事前準備の有無や行った準備の内容により離婚問題は進め方や結果が変わってくる可能性があることから、離婚を検討し始めた場合には可能な範囲で準備を行っておくことが重要です。
※結婚した3組に1組が離婚すると言われているのは、統計上、男性または女性が平均して一生の間に離婚する回数が一生の間に結婚する回数の約3分の1となっていることが根拠となっています(厚生労働省「令和4年度離婚に関する統計の概況」)
2 離婚にあたって検討すべき事項

離婚にあたり、少なくとも以下の事項については検討しておく必要があります。
2.1 離婚の原因に関すること
夫婦が署名した離婚届を役所へ提出することで協議離婚が成立するため、夫婦がともに離婚届に署名できる状況のときは離婚原因について検討する必要はないとも考えられます。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否している場合や夫婦の一方の不貞行為が離婚原因となっており慰謝料請求を行うことを予定している場合、また離婚自体は合意できるものの離婚の条件についてなかなか合意できない見通しの場合などには、離婚原因の有無、それを裏付ける証拠の有無及び内容等をきちんと検討しておく必要があります。
2.2 子供に関すること
夫婦の間に子供がいる場合、子供に関する問題として、どちらが親権を取得するか、養育費の金額や支払期間をどのように定めるか、親権者とならない親とお子様の面会の頻度や方法等をどのように定めるかが問題となります。
離婚時に養育費の金額や支払期間について合意していない場合や合意したものの合意書を作成していないという場合、養育費が継続して支払われるかという点について問題が生じやすくなることから、可能な限り離婚時に合意書を作成するか調停等の裁判手続の中で解決をしておくべきです。
また、面会に関しては、離婚時に面会の頻度や方法等を決めていないと面会の頻度や方法等をめぐって事後的に紛争化する可能性があることから、あらかじめ実施可能な面会交流の条件を調整した上で合意しておくことが好ましいといえます。
2.3 経済的な問題に関すること
離婚にあたって決める必要がある経済的な問題としては、財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用が挙げられます。
このうち、財産分与については、離婚が成立した後には相手方の財産状況を把握できなくなることが多いため、離婚前に財産分与を請求するかどうか及び請求する場合の獲得見込額を十分に検討しておく必要があります。
また、離婚までの生活費を婚姻費用といいますが、少なくとも離婚の話合いが長引くという場合にはもれなく請求しておくことが重要です。
2.4 公的支援に関すること
女性の場合、出産や育児を契機として働き方を変えたことなどにより、結婚前よりも収入が減少していることがあります。
そのため、離婚後に経済的にやっていけるのかという点について不安を持たれる女性は少なくありません。
離婚後の経済的な問題については、請求可能な養育費のほかに受けられる公的支援の種類や内容を考慮して離婚後の生活を実際にシミュレーションしておくことが重要です。
まず、一般的な子育て支援として、児童手当、幼児教育・保育の無償化、高等学校等修学支援金制度(高等学校の授業料無償化)があります。
このうち、児童手当については、離婚協議中であっても一定の要件のもとに受給者変更手続を行うことが可能です。
また、ひとり親世帯に対する公的支援としては、児童扶養手当(母子手当)が存在します。
その他に各自治体の独自の子育て支援策として、子供の医療費助成制度、ひとり親家庭の母又は父の医療費助成制度、公営住宅への優先的入居、家賃支援などが存在します(長崎市が実施する子育て支援の内容はこちらをご覧ください。)。
自身の収入や受け取ることができる養育費に加え、上記のような各種支援をあわせて離婚後の生活が経済的に成り立つかを検討しておくことで離婚後に経済的不安がないことが判明したり、経済的不安を無くすために自身の収入をどの程度上げればよいかが分かり転職先等を見つける際の目安とすることが可能となります。
2.5 その他
その他に離婚にあたり検討すべき事項としては、子供の氏を変更するか否か、子供の社会保険の扶養関係をどうするかという点が挙げられます。
これらの事項は離婚の成否や解決内容に影響するわけではないものの、離婚時に整理しておくのがおすすめです。
3 事前に準備した方がよい事項
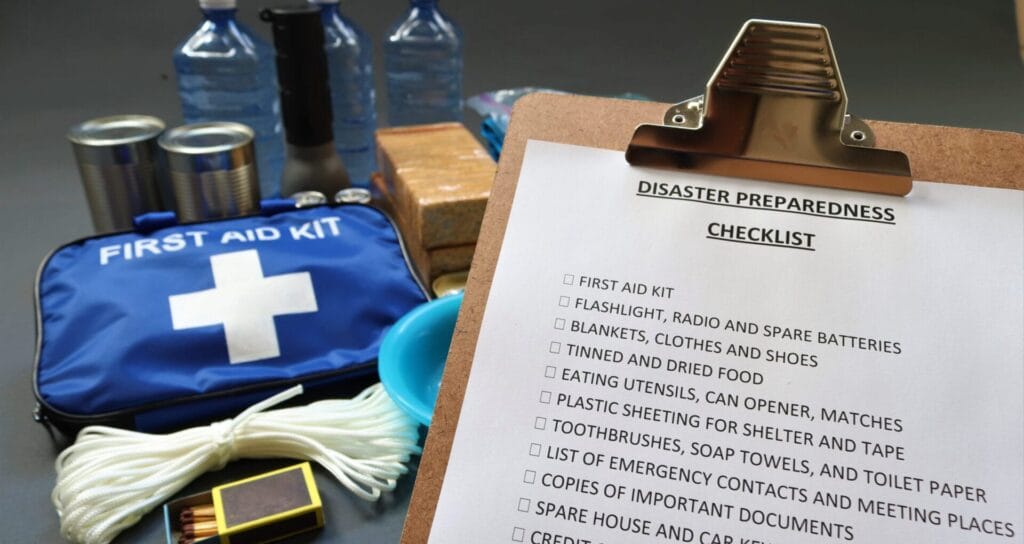
上記のような検討事項との関係で、以下の資料等については事前に準備をする方が好ましいといえます。なお、いったん離婚の話が出てくると準備が難しくなることがあるため、準備を始める時期としては「配偶者に対し離婚の話を切り出す前」というのがおすすめです。
3.1 離婚原因に関する資料の確保
離婚原因に関する資料として、配偶者の不貞行為に関する資料、配偶者によるDV行為に関する資料、別居期間を明らかにする資料などがあります。
このうち、とくに配偶者の不貞行為に関する資料については、配偶者の不貞行為を疑う言動を取った後や離婚の話合いを開始した後には資料収集が困難となる傾向があります。
そのため、配偶者の不貞行為など離婚原因に関する証拠資料は、配偶者を問いただしたり離婚の話合いをする前に収集しておくことが重要です。
3.2 親権の帰属に関する資料の確保
当事者間で子供の親権について合意ができない場合、最終的には家庭裁判所で父母のいずれかが親権者に指定されることになります。
その際、家庭裁判所は、①別居前の監護状況、②別居後の監護状況、③父母の監護能力・監護態勢、④子の意思等を考慮した上、子の利益の観点から父母の一方を親権者に定めるところ、①の別居前の監護状況に関する記録は別居を開始すると収拾が困難になる可能性があります。
そのため、少なくとも親権の取得を希望しているものの判断が分かれ得る事案においては、別居や離婚の話合いを行う前の段階で親権を取得できる可能性をより高めるための生活環境を整え、これを資料化しておくことが重要といえます。夫婦の間に子供がいる場合、子供に関する問題として、どちらが親権を取得するか、養育費の金額や支払期間をどのように定めるか、親権者とならない親とお子様の面会の頻度や方法等をどのように定めるかが問題となります。
3.3 配偶者の収入状況の把握
養育費や婚姻費用は当事者双方の収入を基礎として金額を決定することになるため、養育費等を決める前提として夫婦の収入額を明らかにする必要があります。
しかし、別居後に配偶者に収入証明資料の開示を求めたものの配偶者がこれを開示せず、養育費や婚姻費用の話合いが無用に長期化する場合があります。
このような事態をあらかじめ防止しできる限りスムーズに離婚問題を解決するためには、別居や離婚の話合いを行う前に、源泉徴収票などにより配偶者の収入状況をできる限り正確に把握しておくことが重要です。
3.4 配偶者の財産状況の把握
財産分与を行う前提として、夫婦の財産内容やその評価額を明らかにする必要があります。
しかし、別居後に財産分与の話合いを始めたところ、配偶者が財産状況を明らかにしてくれないという状況になることが少なくありません。
その場合でも、配偶者の財産状況をある程度把握できているのであれば調査可能なこともあるのですが、配偶者の財産状況を全く把握できていない場合には調査が事実上困難となってしまいます。
相手方の財産状況を明らかにできない場合、明らかになっている範囲で財産分与を行わざるを得ず、夫婦間で著しく不公平な解決になる可能性があります。
とくに婚姻期間が長く一定の夫婦共有財産を築けている場合やいわゆる熟年離婚のため財産分与により取得した財産で老後の生活を営む必要性が高い場合などには、相手方の財産状況を把握で着なかったことが原因で十分に財産分与が行われないことで離婚後の生活が成り立たなくなるおそれもあります。
そのため、別居前かつ離婚の話合いをする前の段階で可能な限り詳細に配偶者の財産状況を把握しておくことが重要です。
なお、事前の準備が終わった後の具体的な進め方については、以下のページをご覧ください。
※本記事では離婚を進める場合に押さえておくべきポイントをご紹介いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、離婚の進め方についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。






