不貞慰謝料は自己破産しても支払う必要がある?弁護士が裁判例をもとに解説!
「配偶者に不倫をされ、慰謝料を請求したいが、相手が自己破産しそうだ」、「不貞行為の慰謝料を請求されたが、借金もあり自己破産を考えている」
このような状況で多くの方が抱くのが、「不貞の慰謝料は、自己破産をしたら支払わなくてよくなるのか?」という疑問です。
結論から申し上げると、不貞相手(夫婦以外の者)が負うべき不貞慰謝料は原則として自己破産で免責(支払い義務が免除)されますが、例外的に免責されない悪質なケースもあります。
一方、夫婦のうち不貞行為を行った者が負うべき不貞慰謝料は、裁判例による限り免責されない可能性も考えられます。
この記事では、どのような場合に不貞慰謝料が免責され、どのような場合に免責されないのか、法律のルールと実際の裁判例をもとに、弁護士が分かりやすく解説します。
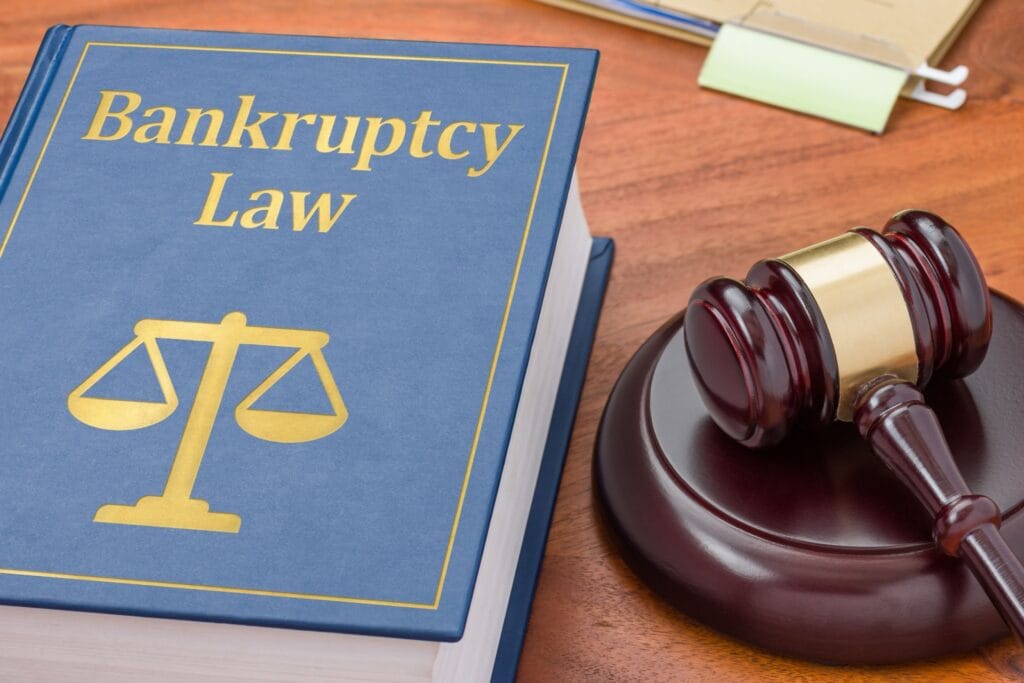
1 自己破産しても支払い義務が残る「非免責債権」とは?
破産して免責許可決定が出た場合、基本的にはそれまで抱えていた借金を法律上弁済する責任はなくなります(これを免責といいます。)。
しかし、全ての債務が免責の対象となるわけではなく、非免責債権にあたる破産債権や財団債権については免責許可決定が出たとしても弁済する責任が残ります。
税金や養育費などがその代表例です。
不貞行為に係る慰謝料請求権は、財団債権にあたらないため、免責されるかどうかは「悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)として非免責債権にあたるかどうかで決まります。
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
1 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
2 「悪意で加えた不法行為」とは?
では、「悪意で加えた不法行為」とは何でしょうか。
最大のポイントは「悪意」という言葉の意味です。
「悪意」の意味について、「害意(他人を害する積極的な意欲)」と捉える見解と通常の「故意」と捉える見解がありました(伊藤眞ほか『条解破産法 第3版』(弘文堂・2020年))。
しかし、現行法で「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(破産法253条1項3号)が非免責債権として規定され、「悪意」と「故意」が明確に書き分けられたことにより、「悪意」を「害意」と解することに争いはなくなりました。
3 裁判例の検討
実際の裁判ではどのように判断されているのでしょうか。免責が認められたケースと、認められなかったケースのポイントを見ていきましょう。
3.1 免責を認めた裁判例
不貞相手に対する慰謝料請求権について、「破産法253条1項2号は「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権である旨規定するところ,同項3号が「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」と規定していることや破産法が非免責債権を設けた趣旨及び目的に照らすと,そこでいう「悪意」とは故意を超えた積極的な害意をいうものと解するのが相当である。本件においては,上記認定及び説示したとおり,被告の,Aとの不貞行為の態様及び不貞関係発覚直後の原告に対する対応など,本件に顕れた一切の事情に鑑みると,被告の不法行為はその違法性の程度が低いとは到底いえない。しかしながら他方で,本件に顕れた一切事情から窺われる共同不法行為者であるAの行為をも考慮すると,被告が一方的にAを篭絡して原告の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず,原告に対する積極的な害意があったということはできない。原告の被告に対する慰謝料請求権は破産法253条1項2号所定の非免責債権には該当しないといわざるを得ない。よって,原告の慰謝料請求権につき,被告は法律的には責任を免れ,強制執行を予定した債務名義たる判決においてその請求を認容することはできないこととなったというほかはない。」として免責を認めた。
不貞相手に対する慰謝料請求権について、「破産法253条1項2号は,「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権とする旨を規定しているところ,同号にいう「悪意」は,単なる故意ではなく,他人を害する積極的な意欲,すなわち「害意」をいうものと解するのが相当である。ここで,不貞行為が不法行為となるのは,婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであることに鑑みると,夫婦の一方と共に不貞行為を行った者が,当該夫婦の他方が有する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するとの認識を有するだけでは,故意が認められるにとどまる。このような者に害意を認めるためには,当該婚姻関係に対し社会生活上の実質的基礎を失わせるべく不当に干渉する意図があったことを要するものというべきである。 これを本件についてみるに,既に認定説示したところに照らし,被告及びAの不貞関係において,被告が一方的にAを篭絡して本件不貞行為に及んだなどの事情は認められない上,Aは,原告と別居した際,未成年の子を連れておらず,夫婦共有財産を持ち出したものでもなく(原告本人〔調書28,29頁〕,弁論の全趣旨),被告がAに対しこれらの行為を唆したともいえない。そうすると,本件不貞行為の際,被告において,本件婚姻関係に対し社会生活上の実質的基礎を失わせるべく不当に干渉する意図,すなわち原告に対する害意があったとまでは認められない。なお,被告が,Aに対し,離婚に関する制度や法的手続等を教示したか否かは,上記認定を左右する事情とはいえない。
したがって,原告は,本件不貞行為による不法行為に基づき,被告に対し,損害賠償請求権を有するが,当該請求権は,破産法253条1項2号所定の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に当たるものとはいえず,本件決定による免責の対象に含まれるものというべきである。」として免責を認めた。
不貞相手に対する慰謝料請求権について、「(1) 破産法253条1項2号は,「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権である旨規定するところ,同号は,当該不法行為の加害者に対する制裁,被害者の救済,加害者の人格的・道義的責任の側面という趣旨から規定されたものと解される。同号のこのような趣旨に加え,同項3号が「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」と規定していることを併せ考慮すると,同号にいう「悪意」とは,故意を超えた積極的な加害意思,すなわち害意を意味すると解するのが相当である。これに反する被告の主張は採用することができない。
(2)そもそも,既婚者と不貞行為に及ぶことがその配偶者に対する関係で不法行為となるのは,当該配偶者の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであるところ,このことに鑑みると,既婚者と不貞行為に及んだ者において,その配偶者が有する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するという認識を有していたというだけでは,故意が認められるにとどまるものである。
そこで検討するに,認定事実によっては,原告が被告に対して害意を有していたと認めることはできない。すなわち,①原告は,Aとの不貞行為を継続する中で,少なくとも被告が血圧に関連する疾病のため入院し,場合によっては命にかかわる状態であることを認識していたものであるが(認定事実(2)),原告においてAとの不貞行為の継続中に被告の病気を知ったことにより,被告に対する認識が害意に転化するものとはいえない。また,②原告が,Aとの不貞行為が被告に発覚した後も同不貞行為を継続し,Aと被告との婚姻関係が終了する前から同棲生活を開始したこと(認定事実(11))も,不貞行為における加害者の故意を超える害意を基礎づけるものとはいえない。そして,③原告は,土平弁護士らが発出した通知書を無視(このうち内容証明郵便については他人を装って受領を拒絶)しているところ(認定事実(9)),このような原告の行為は,被告からの責任追及を意図的に回避しようとするものと評価することができるものの,被告に対する害意があったと評価することはできない。
そして,証拠(原告本人)によれば,原告においては,Aとの新生活を早く始めたいという願望を抱き,また,被告が病を得たことを知ってその死を望むような心境に至ったこともあったことが認められるが,不貞行為に及ぶ者は,その相手方たる既婚者に対する恋愛感情ゆえにその独占を志向するのが一般というべきであるから,上記のような願望ないし心境も,不貞行為における故意に内包されるものというべきである。
そのほか,原告において被告に対する害意を有していたと認めるに足りる証拠はない。
(3)なお,証拠(甲4,乙21)によれば,原告において破産手続開始及び免責許可の申立てをした際に負担していた債務は,本件請求権に係る債務のほかには,パルティール債権回収株式会社が楽天カード株式会社から譲渡を受けたショッピング・カードローン債権に係る債務(元金27万0597円並びにこれに対する利息及び遅延損害金)しかなかったことが認められるが,このことは,原告がAとの不貞行為に当たって被告に対する害意を有していたとは認められないという前記(2)の結論を左右するものではない。」として免責を認めた。
3.2 非免責とした裁判例
配偶者であった者に対する和解金請求権について、以下のとおり「悪意で加えた不法行為 に基づく損害賠償請求権」にあたるとして非免責とした。
「1(1) 脅迫行為(本件和解①前段)について
当該行為の内容が害悪の告知を要素とする脅迫であること,前記認定事実のとおり,それをわざわざ本件和解において示談書に記載した上で一方的に陳謝していること,被告において原告を刑事告訴するか否かが慰謝料の履行の有無にかからしめられていたことからすれば,原告の行為は「悪意」(すなわち被害者への加害の意図)ある行為であったと推認され,これを覆すに足りる的確な証拠はない。
(2) 不貞行為(本件和解①後段)について
前記認定事実のとおり,原告は平成18年に一度不貞行為をし,今後そのような行為に及ばない旨誓約しながらも,Aとの不貞行為に及んだものである。少なくともそのような経緯のある本件については,余程の特殊事情がない限りは,「悪意」がある行為であったと推認されるというべきである。然るに,前記認定事実のとおり,原告は,示談書にて不貞を陳謝し,他の事情と相俟って多額の慰謝料の支払を認めており,この点からすれば,Aとの不貞行為については弁解の余地のないものであったと推認され(当然のことながら,上記した「悪意」の存在を否定する余程の特殊事情などはなかったものと推認され),これを覆す的確な証拠はない。
(3) 離婚について
前記(1)(2)が離婚の大きな原因となっていると評価できることからすれば,原告の「悪意」ある不法行為により被告において離婚を余儀なくされたといえるから,本件和解金支払請求権は全体として非免責債権に該当するというべきである(多額の借金を負い債務整理を要する事態となったり,被告のカード・貯金や子の預金を注ぎ込んだりするなど,原告には生活に影響を及ぼすほどのギャンブル(パチスロ)への依存傾向があり,これを憂慮した被告が治療を勧めたのを原告が拒否したという経緯(この限度で概ね当事者間に争いがない。さらに,証拠(乙2,3)及び弁論の全趣旨によれば,その後もパチスロを続けていたと認められる。)がある中で,再度の不貞行為や脅迫行為が生じたことからすれば,不貞行為さらに上記脅迫行為を経て離婚に至る経緯に「悪意」を否定する要素は見出せない。)。 (4) 以上によれば,本件和解金請求権は,全体として,非免責債権に該当するというべきである。」
配偶者であった者に対する慰謝料請求権について、以下のとおり「悪意で加えた不法行為 に基づく損害賠償請求権」にあたるとして非免責とした。
「(2) 本件不貞行為2の存否について
本件旅行に関し、①被告がBとチャットアプリで知り合い、令和2年2月8日(以下、本項の記載においては、令和2年2月の出来事については年月の記載を省略することがある。)に同人に会いに名古屋市を訪れ、同市内のホテルに宿泊したこと(前提事実2(2))、②被告が本件旅行に当たり、原告に対し、友人と旅行に行く旨の虚偽の説明をしていたことは、当事者間に争いがない。そして、証拠(甲10の1及び2、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、③本件旅行において宿泊することは出発前から計画されていたものであること、④被告は本件旅行を友人との旅行と見せかけるために、8日の出発時に友人に駅まで来てもらって写真を撮影し、原告に送信していたこと、⑤その後、9日に原告が当該友人に連絡をしたことから、被告が嘘をついて本件旅行をしたことが発覚したこと、⑥9日に被告が東京へ戻ったのは午後9時を過ぎた時刻であったことが認められる。
ところで、本件旅行中の被告の行動は、被告の供述によれば、8日午後2時に名古屋駅に到着し、夕方頃に仕事を終えたBと合流して名古屋市内の水族館へ行き、その後Bと食事をした後、被告は一人でホテルに宿泊した、翌9日はBと再び会い、一緒に商店街を訪れるなどした、というものであるところ、かかる供述を前提としても、被告が本件旅行中にBと二人で過ごした時間は長時間に及んでいたということができる。そして、その後、同年2月17日、3月19日、5月8日、同月9日における被告又はBによるツイッター上への投稿からも、両名の交際が継続していた様子がうかがわれることからすると(甲2の1~5)、本件旅行中に両名が長時間にわたり親密な時間を過ごしたことによってその後の交際継続へとつながったものと考えられる。
これに加えて、チャットアプリで知り合った男性に東京から名古屋まで会いに行くだけならば日帰り旅行でも十分可能であるところ、幼い子らを預け、友人の協力を得て原告に虚偽の説明をしてまで、宿泊を伴う本件旅行を計画、実行したことに鑑みると、被告とBは本件旅行中に不貞行為を行ったと考えるのが自然である。
以上に照らせば、本件旅行中にBと不貞行為を行わなかったとの被告の供述は採用することができず、被告がBと会うために宿泊を伴う旅行を行った事実及び上記認定の各事実を総合考慮して、本件不貞行為2の事実を推認するのが相当である。
(3) 本件不貞行為2に係る被告の不法行為責任について
ア 被告は、本件不貞行為2の前には原告と被告との婚姻関係は既に破綻していたと主張する。
しかし、原告と被告は、平成29年4月に婚姻後、同年○月に長女を、令和元年○月に二女をもうけ(前提事実1(1))、原告が生活費を稼ぎ、被告が家事や育児を行うという役割分担の下に、同居して子らを養育する夫婦の生活を継続していたのであり、本件旅行の前には、被告から離婚の意思を伝えたり原告と被告との間で離婚に関する話合いが行われるなどしたことはなかった(被告本人、弁論の全趣旨)。また、原告と被告は、令和2年4月13日には結婚式を挙げることを予定していたところ、本件旅行後の話合いで協議離婚をすることを決めるまでの間に、式場のキャンセルの問題が生じたことはなかった(甲11、弁論の全趣旨)。
これらに照らせば、本件不貞行為2の前に原告と被告との婚姻関係が破綻していたということはできないから、同不貞行為は原告に対する不法行為を構成する。」
「ウ 被告は、本件不貞行為2に係る慰謝料請求権は、本件免責許可の効力により消滅している旨主張する。
しかし、上記(2)及び上記アの認定事実を前提とすれば、被告は、原告の貞操権を侵害することを知りながら、あえて本件不貞行為2に及んだものといえるから、同不貞行為に係る慰謝料請求権は、破産法253条1項2号に定める「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するというべきである。
したがって、破産法253条1項ただし書により、被告は本件不貞行為2に係る慰謝料請求権について責任を免れることができない。 エ 以上によれば、被告の上記主張はいずれも採用することができず、被告は原告に対し本件不貞行為2に係る不法行為責任を負う。」
3.3 裁判例の検討
不貞相手に対する慰謝料請求権が問題となった裁判例①~③は、「悪意」とは故意を超えた積極的な害意をいうものと解すること(裁判例①)を前提として、「被告が一方的にAを篭絡して原告の家庭の平穏を侵害する意図」(裁判例①)、「本件不貞行為の際,被告において,本件婚姻関係に対し社会生活上の実質的基礎を失わせるべく不当に干渉する意図」(裁判例②)がないことを理由に不貞行為が「悪意で加えた不法行為」にあたらないと判断しています。
一方、配偶者に対する慰謝料請求権等が問題となった裁判例④~⑤では、不貞行為が「「悪意で加えた不法行為」にあたると判断しています。
その理由としては、過去に一度不貞行為を行い、今後は不貞行為を行わない旨の誓約をしたにもかかわらず再度不貞行為を行ったこと(裁判例④)のほか、一方配偶者による不貞行為は他方配偶者の貞操権侵害となること(裁判例⑤)が挙げられています。
これらの裁判例を前提とする限り、不貞相手(夫婦以外の者)との関係では不貞行為は明確な害意があるような例外的な場合に限り「悪意で加えた不法行為」にあたると判断される一方、夫婦間では不貞行為は離婚原因(民法770条1項1号)にあたることもあり明確な害意がない場合でも「悪意で加えた不法行為」にあたると認定される可能性があるといえます。
検討結果を表にまとめると以下のとおりとなります。
| 不貞相手への慰謝料 | 不貞した配偶者への慰謝料 | |
|---|---|---|
| 裁判例の傾向 | 原則、免責される。 ただし、積極的に夫婦関係を破壊する「害意」がある場合は免責されない。 | 免責されない可能性あり。 不貞相手への慰謝料とは異なる判断がなされる可能性が否定できない。 |
※本記事では「不貞慰謝料は自己破産しても支払う必要があるか?」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、法律問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。

