住民票の異動忘れで職権消除?知っておくべき影響と住所再設定の方法
Question
住民票の異動手続きを忘れていたら、いつの間にか住民票が『職権消除』されていたようです。「職権消除」とは何ですか?
生活にどんな影響があるのでしょうか? そして、どうすれば元に戻せるのですか?
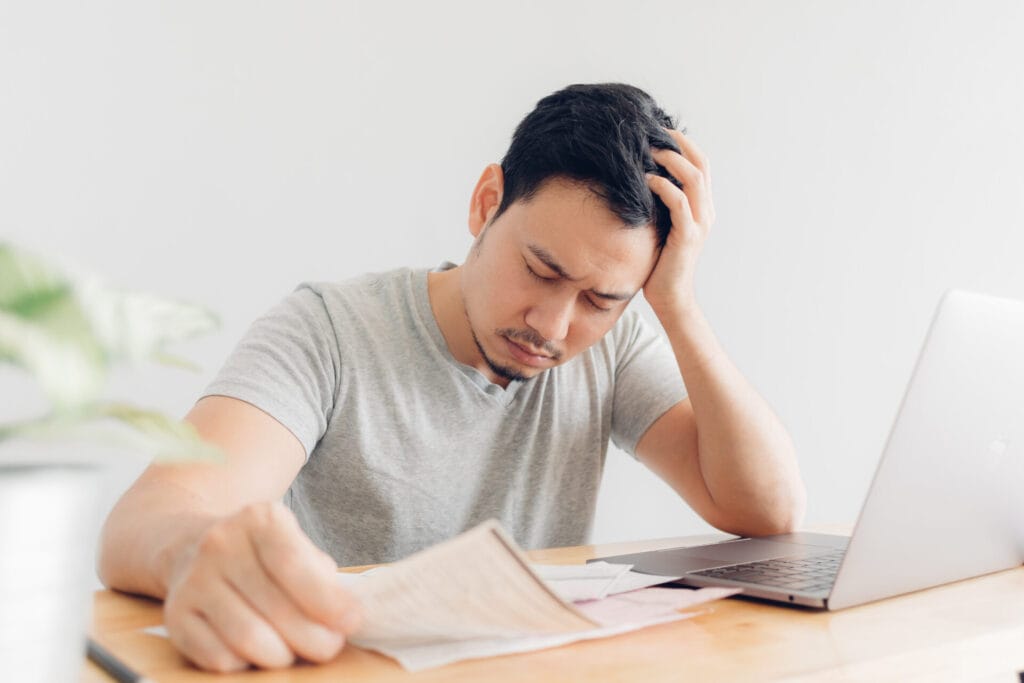
Answer
住民票の「職権消除」とは、市区町村が「実際にはそこに住んでいない」と判断した場合に、届出がなくとも住民票を消除する手続のことです。
職権消除されると、主に以下の4つの大きな影響があり、日常生活に深刻な支障が出ることがあります。
1 役所の手続ができなくなる(住民票の写しや印鑑証明が取れない等)
2 国民健康保険や介護保険が使えなくなる(資格を失うため)
3 国民年金の手続に支障が出る(保険料納付や将来の受給に影響)
4 選挙権の行使に制限が出る
しかし、ご安心ください。職権消除されてしまっても、現在お住まいの市区町村で手続きをすれば、住民票を再設定できます。
この記事では、職権消除による具体的な影響と、住所の再設定方法について、分かりやすく解説します。
なお、住民票が職権消除されている相手へ裁判を起こしたいという場合は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:【住民票が職権消除】相手の住所が不明でも訴訟できる?
1 住民票の職権消除による影響
引越し等を行った場合には住民票の異動をする必要があります。
この手続を怠っていると、市区町村長が住民票を職権で消除することがあります(住民基本台帳法8条、同施行令12条)。
住民票が職権消除されると、その人には住民票上の住所がない状態となります。
その結果、住民票が職権消除された人は以下のような影響を受けます。
1.1 行政サービス(住民票の写しの発行、印鑑登録証明書の発行など)の停止
住民票が職権で消除されると、その市区町村の住民と扱われなくなるため、日常生活で必要となる多くの行政サービスが受けられなくなってしまいます。
具体的に困ることの例:
・住民票の写しが発行できない
・印鑑登録ができず、印鑑登録証明書も発行できない
・その他、その市区町村の住民であることを前提とした各種申請や証明書の取得が困難になる
これは、行政サービスが基本的にその地域に住んでいる住民を対象としているためです。 (根拠:住民基本台帳法第12条第1項、各自治体の印鑑条例(例:長崎市印鑑条例第2条第1項)など)
住民基本台帳法12条1項
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
長崎市印鑑条例2条1項
印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
1.2 国民健康保険や介護保険の資格喪失
国民健康保険や介護保険の被保険者資格は住民票に基づいて管理されています。 そのため、住民票が職権消除された場合、国民健康保険や介護保険の受給資格を喪失することとなります。
国民健康保険法5条
都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」(平成4年3月31日保険発第40号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)
1 職権による資格の喪失確認にあたっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下、「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携をとり行うものとすること。
2 不現住であることの認定は、必ず吏員により、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の趣旨に沿って行うこと。
3 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日であること。
4 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくこと。
5 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導すること。
6 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理すること。
この場合、関係書類の保管期限は、五年とすること。
7 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による資格の喪失確認処理をする際は、合議制により調査内容を十分検討し、住所認定に関しては住民基本台帳担当部署と連絡調整するなど、適正な手順を経て、慎重に取り扱われるよう配慮すること。
なお、具体的な処理に当たっては、各保険者において、それぞれの実情を考慮しつつ、取扱要領を定めること。
介護保険法9条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
1.3 国民年金の未納期間発生や受給停止のリスク
住民票が職権消除されると、年金事務所が住所を把握できなくなり「居所未登録者」として扱われます。
これにより、国民年金に関して以下のような影響が生じます。
関連リンク:日本年金機構Webサイト
未だ年金を受給していない方
年金事務所から納付書が届かなくなり、保険料の納付ができません。
その結果、保険料が未納となり、将来受け取れる年金額が減ってしまったり、年金を受け取れなくなるおそれがあります。
すでに年金を受給している方
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で生存確認が取れなくなるため、原則として毎年「現況届」の提出が必要になります。
この「現況届」を提出しないと、年金の支払いが一時的に止められてしまいます。
これらの取り扱いは、厚生労働省や日本年金機構の通知に基づいて行われています。
「住所が不明な被保険者の取扱いについて(通知)」((平成25年4月1日年管管発0401第5号日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
国民年金法(以下「法」という。)第7条の規定による第1号被保険者又は第3号被保険者(以下「被保険者」という。)が、届け出されている住所に居住しなくなり、住所の届出をせずに行方が分からなくなった場合などにおいては、納付書等の送達ができず、保険料の徴収ができない被保険者となることから、「居所未登録者」として他の被保険者と分けて取扱う必要がある。
こうした被保険者の取扱いについては、「住所が不明な被保険者の取扱いについて(通知)」(平成18年10月4日庁保険発第1004001号社会保険庁運営部年金保険課長通知。以下「平成18年通知」という。)により実施しているところであるが、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正等を踏まえ、今後、本事務の実施に当たっては、下記の事項に留意し、遺憾のないよう取扱われたい。
本通知等に基づく事務に関し、具体的方法(事務処理手順、事務処理上の添付書類等)や進捗管理手順(報告様式等)等を改める必要がある場合には、日本年金機構(以下「機構」という。)の業務処理マニュアル等によりその取扱いを定めること。
なお、これに伴い平成18年通知は廃止する。
記
1 国民年金被保険者を居所未登録者とする要件
居所未登録とする被保険者は、次の(1)~(3)に掲げる者とすること。
(1) 転出届を提出したにもかかわらず転入の事実が確認できない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民調査(住民基本台帳法第34条の規定による調査をいう。以下同じ。)により、住民票が職権消除された者(以下「職権消除者等」という。)
(2) 住民票はあるが、その住所に送付した納付書等が送達不能となり、現地調査において次のいずれかに該当し、住所地に居住していないことが確認できた者(以下「行方不明者」という。)
なお、行方不明者が外国人であるときは、下記ア~エの他に、「改正法施行後における出入(帰)国記録等に係る照会に当たっての留意事項について(依頼)」(平成24年6月11日法務省管総第3508号)に基づき法務省東京入国管理局長(以下「東京入国管理局」という。)に出国の有無等についての照会を行い、再入国許可を受けて海外転出したことが確認できた場合に限り居所未登録者とすること。
ア 住所地に家屋が存在せず、第三者(近隣住民、民生委員、不動産業者等をいう。以下同じ。)への聞き取りによっても居住地の確認ができなかったもの
イ 住所地に家屋は存在するが、居住の形跡が認められず(郵便物の滞留、電気、ガス等の使用状況等により空き家であることの判断)、第三者への聞き取りから、居住していない旨及び転居先が不明である旨の証言があったもの
ウ 住所地に家屋は存在するが、被保険者及び連帯納付義務者(法第88条の規定により保険料を納付しなければならない者をいう。以下同じ。)以外の者が居住しており、その者及び第三者への聞き取りから、居住していない旨及び転居先が不明である旨の証言があったもの
エ 住所地に家屋は存在するが、親族(連帯納付義務者を除く。以下同じ。)が居住しており、現に居住している親族から居住していない旨及び当該親族も本人への連絡がとれない旨の証言があったもの
(3) 国民年金保険料収納事業(市場化テスト)受託事業者等の戸別訪問により、住所地に居住していない旨の報告があり、職員による現地調査の結果、上記(2)のア~エのいずれかに該当する者
2 居所未登録者の取扱
(1) 居所未登録者については、その該当する要件に応じて、次のとおり取扱うこと。
ア 職権消除者等
市町村から国民年金市町村事務処理基準(平成12年2月18日付庁保発第3号社会保険庁運営部長通知。以下「事務処理基準」という。)第15条第3項により居所未登録者報告書が送付された場合は、転入届未提出者(転出届に基づき住民票が消除されたが、転出先市町村への転入届の提出がなく、その住民票が消除された日から3箇月を経過した者をいう。)については、住民票が消除された日から3箇月を経過した日をもって、住民調査者(住民調査により住民票が職権で消除された者をいう。)については、住民票が消除された日をもって、いずれも居所未登録者とすること。
イ 行方不明者
(ア) 納付書等が送達不能となった場合には、未送達登録処理を行い、未送達者一覧表により現況を管理するとともに、転出届の提出の有無についての確認及び現地調査を実施し、転居先は不明であるが住所地に居住していないことが確認できた場合は現地調査の日をもって居所未登録者とすること。なお、現地調査における第三者への聞き取りから、明確に転居日が確定できる場合については、転居日をもって居所未登録者とすること。
(イ) 行方不明者が外国人である場合は、上記(ア)に加えて東京入国管理局に出国の有無についての照会を行い、東京入国管理局からの回答により、次の①~④のとおり取扱うこと。
なお、住民基本台帳法第30条の50の規定に基づく法務大臣からの通知があったことにより、市町村が住民票を消除したときに、事務処理基準第15条第5項に基づき居所未登録者報告書が送付された場合は、住民票が消除された日をもって、資格喪失させること。
① 再入国許可を受けて出国した者については、出国日をもって居所未登録者とすること。
② 再入国許可を受けずに出国した者については、出国日の翌日をもって資格喪失処理を行うこと。
③ みなし再入国許可により出国した者については、居所未登録及び資格喪失いずれの処理も行わないこと。
④ 出国していない者については、(ア)によること。
(2) 居所未登録者として管理する被保険者のうち、上記1(2)のイ又はエの要件により居所未登録者として登録した者については、居所未登録とした日から1年後を目途に同要件に該当するかどうかの確認を行うこと。なお、その後も引き続き居所未登録者として管理する被保険者については、同様の確認を定期的に行い、納付書等が送付されないことにより、保険料の納付や免除申請の機会が失われることのないよう配慮すること。
1.4 選挙権の行使制限
住民票の消除がされると、市町村長からの通知(住民基本台帳法15条2項、公職選挙法29条1項)に基づき、住所を有しなくなった旨の表示(公職選挙法27条1項)がされ、その後選挙人名簿から抹消されます(同法28条2号)。
その結果、住民票が職権消除された者は、選挙権の行使が制限されることになります。
「住民票の消除がされると,住民基本台帳法15条2項,公職選挙法29条1項の規定に基づく市町村長からの通知に基づいて同法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示がされ,その後さらに同法28条2号の規定により選挙人名簿から抹消されることにより,その者の選挙権の行使が制限されることになるところ,住民票の消除は同法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示をするための法律上の要件とはされていない。しかしながら,住民票の消除は,住民基本台帳法24条に基づく転出届等に基づき又は職権によりその者が市町村の区域内に住所を有しなくなったものと認めて行うものであり,同法上,市町村長は,その事務を管理し,及び執行することにより,又は同法10条,12条の3若しくは13条の規定による通知若しくは通報若しくは同法34条1項若しくは2項の調査によって住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知ったときは届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない(14条1項)などとされていることからすれば,住民票の消除がされた者は当該市町村の区域内に住所を有しなくなった高度の蓋然性が存するということができる上,住民基本台帳法15条2項,公職選挙法29条1項の各規定に照らすと,同法は住民基本台帳法15条2項に基づく市町村長からの住民票の消除の通知に基づいて当該市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に公職選挙法27条1項の規定による住所を有しなくなった旨の表示をすることを予定しているものということができる。そうであるとすれば,住民票の消除は,選挙権の行使の制限という法的効果をもたらす行政処分ということができる。」
関連リンク:裁判所Webサイト
2 住民票が職権消除された場合どうすればよい?
2.1 役所での手続と必要書類
住民票が職権消除された場合でも、現在の住所地の市区町村の窓口で住所を再設定することが可能です。
手続きには、まずご本人であることを確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が必要です。
加えて、自治体によっては、現在のお住まいを証明する書類(賃貸借契約書、公共料金の領収書など)や、戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍の附票などの提出を求められる場合があります。
事前に役所のホームページで確認するか、電話で問い合わせておくとスムーズです。
2.2 本人確認書類がない場合はどうしたらよい?
住民票が職権消除されている場合、住民票上の住所に紐づく本人確認書類も保有していないということが少なくありません。
このような場合、本人確認書類がなくても役所の担当者の各種聴聞等を経て住所設定を行うことができます(「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)」(令和2年6月17日付総行住第114 号総務省自治行政局住民制度課長通知))ので、ひとまず現在居住している市区町村の窓口へご相談ください。
関連リンク:総務省Webサイト|「ホームレス等に対する住所認定の取扱いについて(通知)」
※本記事では「住民票が職権消除された場合の影響と住所の再設定方法」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、離婚届の提出についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。

