
Q&A

Q&A
17条決定に異議申立てを行うとどうなる?調停終了と訴訟移行を弁護士が解説
民事調停で話合いが決裂したのですが、裁判所から調停に代わる決定(17条決定)が出されました。
内容に納得がいかないので異議を申し立てたいのですが、そうすると、また話し合い(調停)が再開されるのでしょうか?それとも、裁判(訴訟)になってしまうのでしょうか?
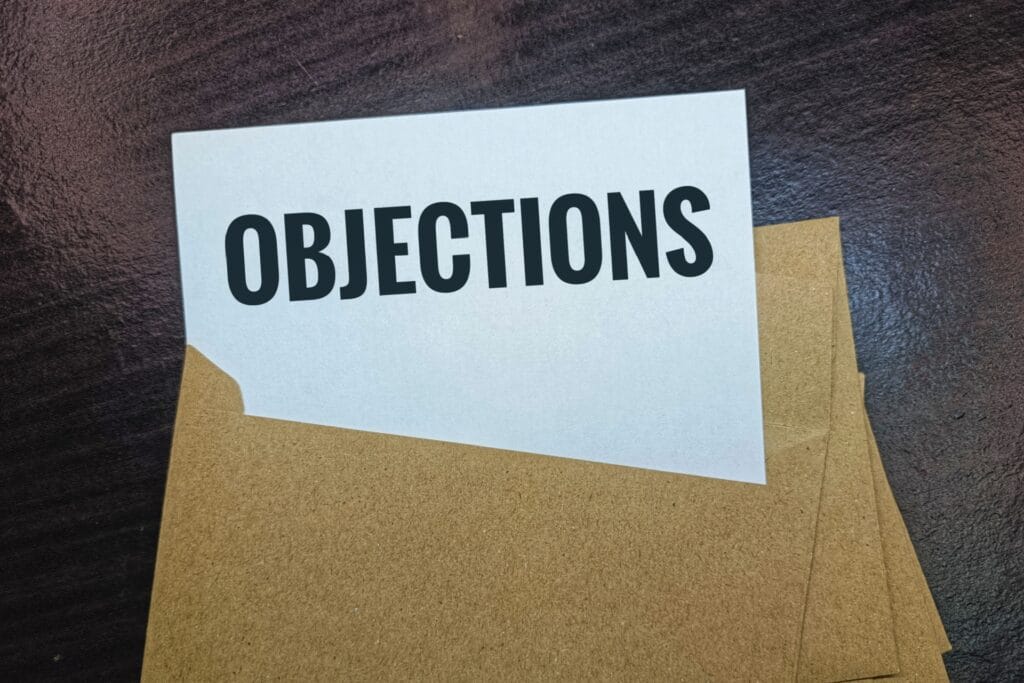
Answer
17条決定に異議を申し立てると、調停手続はその時点で終了し、再開されることはありません。
決定内容に納得できず、引き続き争うことをご希望の場合は、訴訟から調停に移っていた事件(付調停事件)などを除き、ご自身で新たに「訴訟」を起こす必要があります。
注意点として、異議申立てやその後の訴訟提起には「2週間」という短い期限が設けられています。
異議申立てについては上記期限内に申立てを行わなければ却下されることになります。
訴訟提起については、上記期限内に手続を進めることで、時効や手数料の面で有利になりますので、迅速な対応が非常に重要です。
1 そもそも「17条決定(調停に代わる決定)」とは?
17条決定(調停に代わる決定)とは、民事調停において、調停が成立する見込みがない場合に裁判所が相当であると認めたときに職権でなされることがある決定です。
民事調停法17条に規定されていることから、一般に17条決定と呼ばれています。
17条決定は、典型的には、当事者間の僅かな意見対立により調停が成立しない場合や一方当事者が手続追行の意欲を失っている場合になされるものです。
17条決定に当事者からの異議申立てがなされず決定が確定した場合、裁判上の和解と同一の効力を有するため、17条決定により紛争解決が期待できます(民事調停法18条5項)。
和解のための17条決定?
令和5年2月28日まで、訴訟期日に和解を成立させるためには、当事者の少なくとも一方が裁判所に出頭している必要がありました(令和4年法律第48号による改正前の民事訴訟法170条3項ただし書)。
そこで、当事者のいずれも裁判所に出頭しない状況で和解を成立させる場合に、裁判所が訴訟事件を調停に付した上で17条決定を行うことがありました。
もっとも、民事訴訟法改正により現在ではいずれの当事者も裁判所に出頭していない場合でも電話会議等により和解を成立させることができるようになったことから、和解を成立させる目的で訴訟事件が調停に付されることは基本的になくなったといえます。
2 17条決定に異議申立てを行うとどうなる?
17条決定に対しては、決定の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てを行うことができ、適法な異議申立てを行うことにより17条決定は効力を失います(民事調停法18条1項、4項)。
では、17条決定に異議申立てを行った場合、調停が再開するのでしょうか、それとも調停は終了し訴訟へ移行するのでしょうか。
この点に関し、17条決定に異議申立てを行った場合における調停の終了時期に関する明文規定は存在しないものの、以下の理由から17条決定に異議申立てを行った場合には調停が終了すると考えられています。
①17条決定は、「調停が成立する見込みがない場合」に、裁判所が職権で行うことができるものであるところ、調停成立の見込みがないにもかかわらず調停を再開する実益がない。
②民事調停法19条は、17条決定に異議申立てがあった場合について、一定期間内に調停の目的となった請求について訴訟提起したときは調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなしている。同規定は17条決定に異議申立てがあった場合には調停事件が終了し、訴訟での紛争解決へ移行すべきことを前提としている。
なお、17条決定に異議申立てを行った場合、訴訟事件が調停に付されたという場合でない限り、自動的に訴訟に移行するわけではなく、別途訴訟提起する必要がある点には注意が必要です。
付調停事件の場合
裁判所が訴訟事件を調停に付した付調停事件の場合、 調停が不成立になったり17条決定に異議申立てがなされ調停が終了したときは中断していた訴訟事件が再開することになります。
そのため、付調停事件において、17条決定に異議申立てを行った場合、別途訴訟を提起し直す必要があるわけではありません。
付調停事件に関しては、詳しくは「訴訟が途中で調停に。不成立になったら裁判はどうなる?【弁護士が解説】」をご覧ください。
3 【訴訟へ進む場合の注意点】2つの「2週間」の期限
3.1 異議申立ての期限
17条決定に対する異議申立ては、決定の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があります。
上記期間経過後に異議申立てがなされた場合、不適法な異議申立てとして却下されることになります(民事調停法18条2項)。
異議申立期間は初日不算入
異議申立期間については、民法の規定に従う(民事調停法22条、非訟事件手続法34条4項、民事訴訟法95条1項、民法140条)ことから、初日不算入となります。
そのため、決定の告知を7月1日に受けた場合、決定の告知を午前0時に受けるということは通常ないことから、異議申立期間は原則として7月2日から2週間以内、すなわち7月15日までとなります。
初日不算入については、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:「1週間後」はいつまで?期間計算で損しないための民法のルール「初日不算入」を弁護士が解説
3.2 訴訟提起の期限
2週間以内に訴訟提起した場合、以下のメリットがあります。
①調停申立て時と訴訟提起時のずれによる不利益を避けることができる
2週間以内に訴訟提起すると、調停申立て時に訴え提起があったものとみなされる(民事調停法19条)ため、訴え提起時を基準にすると消滅時効が完成しているなどの不利益を回避することが可能です。
②手数料(印紙代)が無駄にならない
2週間以内に訴訟提起した場合、調停申立ての際に裁判所へ納めた手数料(印紙代)が、訴訟を起こす際の手数料から差し引かれるため、手数料(印紙代)が無駄になりません(民事訴訟費用等に関する法律5条1項)。
そのため、17条決定に対し異議申立てを行った場合において、調停の申立人が訴訟により解決を目指すのであれば、異議申立ての通知を受けた日から2週間以内に訴訟提起することが推奨されます。
調停の相手方(申し立てられた側)が訴訟提起した場合も上記①②のメリットはある?
民事調停法19条では、「申立人が・・・調停の目的となった請求について訴えを提起したときは」とされているところ、調停の相手方(申し立てられた側)が訴訟提起した場合、上記①及び②のメリットは生じません。
民事調停法第14条(調停の不成立)
調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
民事調停法第17条(調停に代わる決定)
裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
民事調停法第18条(異議の申立て)
1 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立てをすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から二週間とする。
2 裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。
3 前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
4 適法な異議の申立てがあったときは、前条の決定は、その効力を失う。
5 第一項の期間内に異議の申立てがないときは、前条の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
民事調停法第19条(調停不成立等の場合の訴の提起)
第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
民事調停法第19条の2(調停の申立ての取下げ)
調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
民事訴訟費用等に関する法律第5条第1項
民事訴訟法第三百五十五条第二項(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項(第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項(同法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
民事調停法第22条(非訟事件手続法の準用)
特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。
非訟事件手続法第34条(期日及び期間)
4 民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。
民事訴訟法第95条(期間の計算)
1 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

