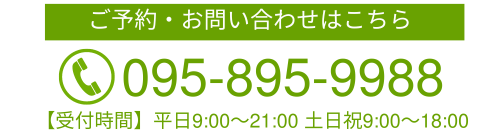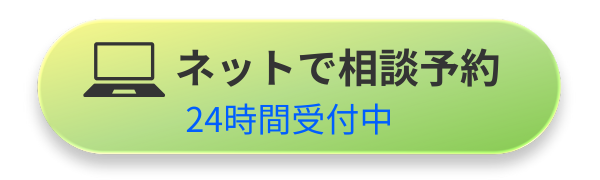遺産分割に関する事例

遺産分割に関する事例
法定相続分とは異なる割合で遺産分割を成立させたMさんの事例
ご相談者Mさん
当事者:事業に使用している不動産の取得を希望する
性別:女性
職業:青色専従者
相手職業:不明
解決方法:協議

※案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集しております。
状況
まだMさんが幼かった頃、Mさんの母は継父と再婚しました。
Mさんと継父の仲は良好ではあったのですが、養子縁組まではしていませんでした。
結婚後、継父と母は数十年にわたり夫婦で事業を営んでいましたが、継父が亡くなったのを機に、MさんとMさんの夫が事業を手伝うようになりました。
その後数年して母も亡くなったため、継父と母が事業のために使用していた継父名義の不動産や、継父と母が居住していた自宅マンションについて相続手続を行おうとしたところ、継父には異父きょうだいが4名いることが判明しました。
継父の異父きょうだいに対しどのように対応すればよいか悩んだMさんは、当事務所の弁護士に異父きょうだいとの間の遺産分割協議等についてご依頼されました。
弁護士の活動
1 方針決定
継父や母には預貯金などの金融資産がほとんどなく、事業用の不動産や自宅マンションなどの不動産があるのみでした。
母の相続が発生した当時、継父や母の事業をMさん夫婦が受け継いでいたことから、Mさんとしては事業に使用する継父名義の不動産については確実に取得したいと希望していました。
そこで、弁護士はMさんと相談の上、「事業用の不動産をMさんが取得し、マンションについては売却後に売却代金を継父の異父きょうだいへ分配する。」との内容の遺産分割を目指すこととしました。
2 継父の異父きょうだいとの間の遺産分割
弁護士は、継父の4名の異父きょうだいに対し、継父のこれまでの生活状況やMさんの現在の生活状況、遺産の内容などを説明した上で、「事業用の不動産はMさんが単独で取得させていただき、自宅マンションは売却した上で売却代金から売却諸経費を控除した残額を法定相続分に応じて分配する。」との内容の遺産分割を提案しました。
その結果、4名の異父きょうだい全員が上記内容での遺産分割に応じてくれることとなりました。
3 遺産分割後の処理
遺産分割協議が成立してから数か月以内に不動産の売却が完了しました。
その後、Mさんは、継父の異父きょうだいから指定された口座へ売却代金の一部を振り込もうとしたのですが、指定された口座情報が誤っていたようで振込みができませんでした。
そこで、弁護士が継父の異父きょうだいに振込先口座を再確認した上、無事に異父きょうだいへの振込みまで完了しました。
ポイント
1 異父きょうだいとの遺産分割
被相続人に異父母きょうだいがいる場合でも、被相続人自身が異父母きょうだいの存在を認識していないということがあります。
また、被相続人は異父母きょうだいの存在を知っていたものの、異父母きょうだい間の交流が全くなかったため、被相続人が自身の配偶者や子供には異父母きょうだいの存在を伝えていなかったということもあります。
そのため、相続人となった方が、予期せず被相続人の異父母きょうだいと遺産分割を行わざるを得ない状況となることがありますが、全く交流がなかった被相続人の異父母きょうだいと連絡を取った上で遺産分割を行うというのは一般の方には容易ではありません。
そこで、被相続人の異父きょうだいとの間で遺産分割を行わざるを得ない状況となった場合には、ひとまず相続問題を多く扱う弁護士に相談した上で、方針をじっくりと検討することをお勧めします。
なお、今回のケースのように遺産分割協議が成立した後も不動産の売却や口座情報の確認など細かな事務連絡を行う必要が生じる場合もあります。
2 法定相続分と異なる割合による遺産分割を希望する場合のポイント
(1)そもそも法定相続分とは何か?
民法は、以下のとおり法定相続分について定めています。
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分は、被相続人が別途相続分の指定をしていない場合における、各共同相続人が被相続人の権利義務を取得する割合を意味しています(民法第898条参照)。
そのため、被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、基本的には法定相続分ないし具体的相続分どおりに遺産分割を行うというのが一般的です。
とはいえ、遺産分割協議や遺産分割調停の中では、法定相続分やこれを前提とする具体的相続分とは異なる分割方法を定めることが可能と考えられています(片岡武・菅野眞一『第4版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』126頁など)。
なお、これは、私的自治の原則のもとでの自律的決定であることを理由とすることから、遺産分割審判により遺産分割審判を行う場合には法定相続分ないし具体的相続分と異なる割合での遺産分割とはなりません。
(2)法定相続分とは異なる割合での遺産分割を希望する場合のポイント
上記のとおり、相続人間で合意できる限り、法定相続分と異なる割合での遺産分割を成立させることが可能です。
もっとも、法定相続分と異なる割合での遺産分割を希望する場合には、以下の3つのポイントを押さえておく必要があります。
①背景事情を理解してもらう
被相続人による指定や当事者間の合意がない場合、遺産分割は法定相続分や具体的相続分に従って行うことになります。
そのため、相続人は、遺産について法定相続分や具体的相続分に応じた割合で取得できるというのが遺産分割の大前提です。
法定相続分と異なる割合での遺産分割を希望するということは、他の相続人に対して当該相続人が本来取得できるはずの財産を譲渡するよう求める行為と実質的に同視できるところ、他の相続人が納得できるだけの事情を説明する必要があります。
そこで、法定相続分と異なる割合での遺産分割を希望する場合には、他の相続人に対し、被相続人の生前の生活状況、相続発生後の死後事務の状況、祭祀承継の状況、遺産の内容、評価額、相続人の生活状況などを説明した上で、法定相続分と異なる割合での遺産分割を希望する理由について他の相続人に納得してもらうことが重要です。
なお、他の相続人の納得を得られないときには法定相続分や具体的相続分どおりの遺産分割を行わざるを得ませんので、その場合には取得する遺産の内容(不動産、預貯金、有価証券などの遺産の中のどの財産を取得するか。)についての希望の実現を目指すべきです。
②相手方が取得する遺産を具体的に伝える
他の相続人に対し法定相続分と異なる割合での遺産分割を求める場合、当該相続人としては自身が取得できる遺産の内容や金額に最も興味を有しています。
そのため、遺産分割案を提案する際には、他の相続人が取得することになる遺産の内容や金額(評価額)をできる限り具体的に伝える必要があります。
③財産状況などについて虚偽の説明は行わない
法定相続分とは異なる割合での遺産分割を希望する場合に、他の相続人に対し遺産の内容や評価額について虚偽の事実を伝えてしまうということは行ってはいけません。
これを行うと、遺産分割協議等が成立しても詐欺取消し(民法第96条第1項)等により遺産分割協議が無効(民法第121条)となり、遺産分割を最初からやり直さなければならなくなる可能性があります。
また、民事的に遺産分割協議のやり直しが必要になる可能性があるだけではなく、場合によっては詐欺罪(刑法第246条)にあたり刑事罰の対象となる可能性も考えられます。
今回のケースでは、被相続人である継父の生前の生活状況や継父とMさんの関係性、遺産である不動産の現在の用途などの背景事情を説明した上、他の相続人が取得する遺産の内容を具体的に伝えた結果、他の相続人は法定相続分とは異なる割合による遺産分割に応じてくれることとなりました。
3 相続発生前の対策
今回は、継父が遺言書を作成していなかったため、継父の異父きょうだいとの間で遺産分割を行わなければなりませんでした。
しかし、もしも継父がMさんの母やMさんに遺産をすべて相続させるとの内容の遺言書を作成していたとすれば継父の異父きょうだいとの間で遺産分割等を行う必要はありませんでした(兄弟姉妹には遺留分がないことから、遺留分侵害額請求を受けることもありません。)。
このように相続問題は相続発生前の対策が重要になることがありますが、あらかじめ遺言書を作成される方というのはあまり多くありません。
また、遺言書を作成するよう勧める行為は、積極的に自身に遺産を相続させるようで憚られる、言われた方に死を想起させてしまうため控えたいなどの理由により、家族間であっても遺言書を作成するように勧めることはハードルがあるように見受けられます。
しかし、遺言書を作成しているかどうかにより残された相続人等が置かれる立場は大きく変わりますので、今回のケースのように家族関係が複雑な場合や特定の財産を特定の相続人に相続させたいという場合には少なくとも弁護士に相談に行くことまでは家族間で話をしていただくことをお勧めします。
※掲載中の解決事例は、当事務所で御依頼をお受けした事例及び当事務所に所属する弁護士が過去に取り扱った事例となります。